介護の仕事をしていると、「もう限界かも」と感じる瞬間に出会うことがあります。
今回は、私が夜勤明けの早朝に経験した出来事から、介護現場の現実、そして利用者様と介護者、それぞれの感情と尊厳について考えてみたいと思います。
介護現場での夜勤明けに起きた出来事
16時間にわたる夜勤勤務があと1時間で終わるというタイミング。
ある男性利用者様の居室に入った瞬間、私は言葉を失いました。
床もベッドも、そしてご本人も便だらけの状態。
強い臭気と混乱した状況に、思わず「心が折れそう…」という気持ちになりました。
弱々しく、繰り返される言葉
この方は普段、少し頑固で、声掛けにも怒り気味になることがある方。
でも、このときは違いました。
「なんでこんなことになっちゃったんだろう…」
「自分でやらないで、呼べばよかった…」
繰り返されるその言葉は、混乱と羞恥心、そして自尊心の傷つきがにじむものでした。
「気がついたらこうなっていたの?」と聞くと、小さく頷かれました。
介護者としての対応と、心の葛藤
もちろん、掃除も介助も大変です。
臭いもきつく、自分も汚れ、疲労も限界。
「なぜ私がこんなことを…」と思う気持ちも、正直ゼロではありませんでした。
それでも、「この方も、望んでこうなったわけじゃない」。
そう思うと、自然と手が動きました。
「大丈夫ですよ」
そう声をかけながら、私は清掃と更衣を行いました。
この方が今感じている戸惑いを少しでも和らげたい、そんな思いでした。
排泄ケアの現場で忘れてはいけないこと
こうした「排泄の失敗」は、介護の現場では日常的にあります。
それでも、そこで感じるのは、
どんなに心身が衰えていても、利用者の“感情”はちゃんと残っているということ。
怒り、恥ずかしさ、悲しみ、戸惑い…
私たち介護者が、その感情にどこまで寄り添えるかが問われる瞬間でもあります。
介護者自身の気持ちのケアも必要
一方で、介護者もまた人間です。
時間に追われ、身体も心も疲弊していくなかで、常に「やさしさ」を保つのは簡単ではありません。
だからこそ、介護者自身の心のケアや、リセットできる環境もとても大切です。
「自分の気持ちを押し込めすぎないこと」――それもまた、長く働くための知恵だと感じます。
介護とテクノロジーが共存する未来に期待して
こういう時、私はふと思います。
AIやテクノロジーの力がもっと介護現場に導入されたら、どれだけの心の余裕が生まれるだろう? と。
汚物の処理や移乗介助など、人間の負担が減れば、
もっと「心の通うケア」に集中できるかもしれない。
介護される側の尊厳を守ると同時に、介護する側の心の健康も守る。
そんな未来に、一歩でも近づけたらと願っています。
まとめ
介護の現場は、身体的にも精神的にも大きな負担があります。
でも、その中で生まれる小さな心の触れ合いは、私たちに人としての原点を思い出させてくれます。
利用者様も、介護者も、同じ「人間」であること。
感情があること。
尊厳があること。
それを忘れずにいられることが、介護における「やさしさ」なのかもしれません。
「誰かの尊厳を守りながら、自分の尊厳も守る」――それが可能な介護の未来に、一歩でも近づいてほしいと、心から願っています。





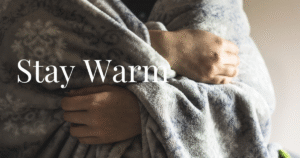
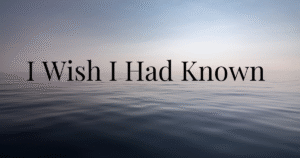
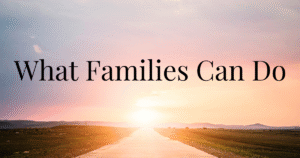


コメント