今年の夏も、危険な暑さが続いていますね。
先日、1ヶ月ぶりに実家へ帰りました。両親の体調が気になっていましたが、ふたりとも元気そうでほっと一安心。とはいえ、やや暑さに疲れている様子も見えました。
部屋はエアコンを27度に設定し、扇風機で効率よく涼しくしていました。水分は日頃からよく摂っていて、母は静岡出身らしく緑茶を欠かしません。この日も水出しの冷たい緑茶が用意されていて、私はそれをいただきましたが、両親は夏でも食後には熱いお茶。昔ながらの習慣が続いていて、どこか安心感を覚えました。
高齢者と夏の危険な暑さ
離れて暮らしていると、この暑さの中どう過ごしているのか心配になるものです。
特に高齢の方は、「昔はエアコンなんて使わなかった」「暑いのは我慢すればいい」という考え方が残っていることがあります。その結果、熱中症や脱水症状に気づかないまま体調を崩すこともあります。
私の両親はテレビやインターネット、新聞などから積極的に情報を取り入れ、きちんと対策をしていました。最近の夏は危険な暑さであることを理解し、庭仕事や犬の散歩も控えて過ごしているとのこと。安心感と同時に、「やはり正しい情報は命を守る」ということを改めて感じました。
高齢者は暑さを感じにくい?
以前、私が勤めていた介護サービスで、一人暮らしの高齢者の方を訪問したことがあります。
真夏にもかかわらず、その方の家にはエアコンがありませんでした。驚いて理由を尋ねると、「大丈夫、慣れてるから」と笑っておられました。
高齢になると、暑さを感じにくくなる背景には次のような理由があります。
- 体温調節機能の低下 皮膚や血管、汗腺の働きが衰え、体温の上昇に対する感覚が鈍くなります。
- 発汗量の減少 汗をかく量が減り、体温が上がっても涼しいと錯覚することがあります。
- 自律神経の衰え 暑さや寒さを感じる感覚を司る自律神経が加齢とともに弱まり、温度変化に反応しづらくなります。
- 昔の習慣や価値観の影響 「昔は扇風機で十分だった」「エアコンは贅沢」という意識が根強く残っている場合があります。
こうした理由から、エアコンがあっても使わない、あるいは使う時間を極端に短くしてしまう高齢者も少なくありません。これは熱中症のリスクを高める大きな要因です。
高齢者の夏バテ予防のポイント
室温・湿度の管理
- エアコンは27℃前後、湿度は50〜60%を目安に
- 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させると効率的
水分補給の工夫
- 水やお茶をこまめに(1日1.5〜2Lを目安)
- 食事やおやつからも水分を摂取(スイカ、みそ汁、冷ややっこなど)
- 冷たすぎない飲み物で胃腸への負担を軽減
栄養バランス
- タンパク質(魚、卵、豆腐)やビタミンB群(豚肉、納豆)で疲労回復
- 夏野菜(トマト、きゅうり、ピーマン)で水分とミネラル補給
紫外線は免疫にも影響する
夏の健康管理で意外と見落とされがちなのが紫外線対策です。
紫外線(特にUVB)は皮膚の細胞にダメージを与え、免疫機能を一時的に抑える働きがあります。これは身体が紫外線による炎症を抑えるための反応ですが、その結果、ウイルスや細菌への抵抗力も下がってしまうのです。
- 局所免疫の低下:日焼けした部分は外敵への防御力が弱まる
- 全身免疫への影響:広範囲の日焼けでは全身の免疫機能が一時的に落ちる
高齢者はもともと免疫力が低下傾向にあるため、紫外線ダメージが加わると感染症や皮膚病のリスクが高まります。
そのため、外出時は日焼け止め、帽子、日傘、長袖などで紫外線を避けることが重要です。
介護者自身の夏バテ対策も大切
私自身も、暑さは我慢しないようにしています。少し前までは「節電のためにエアコンをなるべく使わない」という風潮がありましたが、今は健康を守るための使用が大切だと実感しています。
外出時は日焼け止めを塗るように心がけ、紫外線から肌を守ることも忘れません。紫外線は見た目だけでなく免疫にも影響することを知ってからは、より意識して対策を取るようになりました。水分補給も意識的に行い、無理せず、こまめに休憩を取るようにしています。
離れて暮らす家族への見守りの工夫
もし高齢の家族が遠方に住んでいる場合、定期的な電話や訪問で状況を確認することが大切です。
「今日は暑いから冷房つけてね」と声をかけるだけでも、使うきっかけになります。必要であれば、温湿度計や見守りセンサーの導入も検討すると安心です。
夏は体力を奪う季節ですが、適切な対策で元気に乗り切ることができます。
高齢者の暮らしに寄り添いながら、介護者自身も健康を守ることが、長く続けられる介護の第一歩です。
合わせて読みたい記事


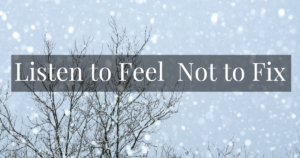



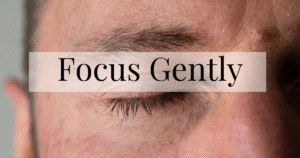

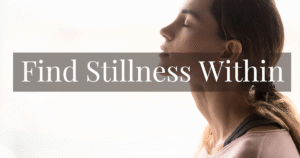
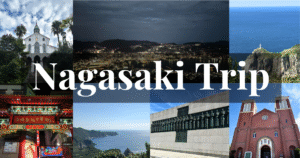
コメント