介護が長引くと、誰もが家の片付けにまで手が回らなくなることがあります。その結果、気づけば「ゴミ屋敷」と呼ばれるような状態になってしまうことも。今回ご紹介するのは、義母と義理の兄が暮らしていた実家を片付ける中で気づいた、「物を片付けることは心を整理することにつながる」という体験談です。
ゴミ屋敷になってしまうのは「怠け」ではない
「家が荒れているのはだらしないから」――そう思われがちですが、実際には違います。
私の夫の実家もそうでした。
7年前、義母を介護していた義理の兄が膵臓癌で亡くなりました。体調が悪くなっても余命宣告を受けるまで病気に気づかず、日常生活や仕事をこなすだけで精一杯。家の片付けどころではなかったのでしょう。
結果として、建築士だった義父が建てた立派な家は「ゴミ屋敷」と呼ばざるを得ない状態になっていました。
これは珍しいことではありません。
介護と病気、生活の負担が重なれば、どんな真面目な人の家でも荒れてしまうのです。
一気に業者へ依頼せず「自分たちで片付ける」選択
私たちは業者に任せることも考えました。しかし夫は、まずは自分の手で一つひとつ片付けていく道を選びました。
- 連休を利用して遠方から通い
- 朝から晩までゴミを分別し、草を刈り
- 休みのたびに少しずつ整理していく
この作業は正直、気の遠くなるような大変さでした。最初は「なぜこんなゴミ屋敷にしてしまったのか」と憤りの気持ちすらありました。
片付けながら気づいた「暮らしの痕跡」
ところが、不思議なことが起きました。
手に取った一つひとつの物を見ているうちに、ただの「ゴミ」ではなく、そこで暮らした義母や義兄の人生の断片として感じられるようになったのです。
- 「お母さんはこの食器を揃えて素敵な食卓を囲んでいたんだな」
- 「お兄さんはこのチョコが好きだったんだな」
- 「この瞬間、この家で暮らしを楽しんでいたんだ」
片付ける手を動かしながら、夫と「きっとこうだったんだね」と語り合う時間は、失った人を少しずつ理解し直し、納得していく過程そのものになっていました。
ゴミ屋敷の片付けが「心の整理」になる理由
心理学的にも、片付けは「回想法」と似た効果があるといわれています。
物を手に取りながら過去を振り返り、その意味を見出すことで、自分自身の気持ちも整理されていくのです。
だからこそ、片付けを通じて「怒り」から「理解」へと感情が変わり、最後は「温泉に入りながらお片付け旅行を楽しむ」という心境にまでたどり着けたのだと思います。
介護後にゴミ屋敷を片付けるときのポイント
同じような状況にある方に向けて、私たちの経験から役立ったことをまとめます。
- すぐに完璧を求めない:1日で片付け切ろうとすると疲弊します。連休や休暇を活用して少しずつ進めましょう。
- 業者に頼む選択も残しておく:体力的に無理を感じたら迷わず依頼。精神的に区切りをつける助けにもなります。
- 一人で抱え込まない:兄弟姉妹や配偶者と一緒に取り組むことで、物語を共有し、心の負担も軽くなります。
- 「思い出」を見つける視点を持つ:ただのゴミではなく、そこに生きた証があると感じると、気持ちが変わります。
終わりに:片付けは生きてきた証を受け止める時間
私たちは今も、義母と義兄の残した家を少しずつ片付けています。
最終的には売却する日が来るでしょう。けれども、この手間をかけてきた時間は、私たち自身の心を整理する大切なプロセスでした。
もしあなたが今、「親の家がゴミ屋敷になってしまった」と悩んでいるなら、片付けは単なる労働ではなく、心の整理をするための大切な時間になるかもしれません。
まずは、今日から1つの引き出しを開けてみる。そこから始めてみてはいかがでしょうか。
合わせて読みたい記事

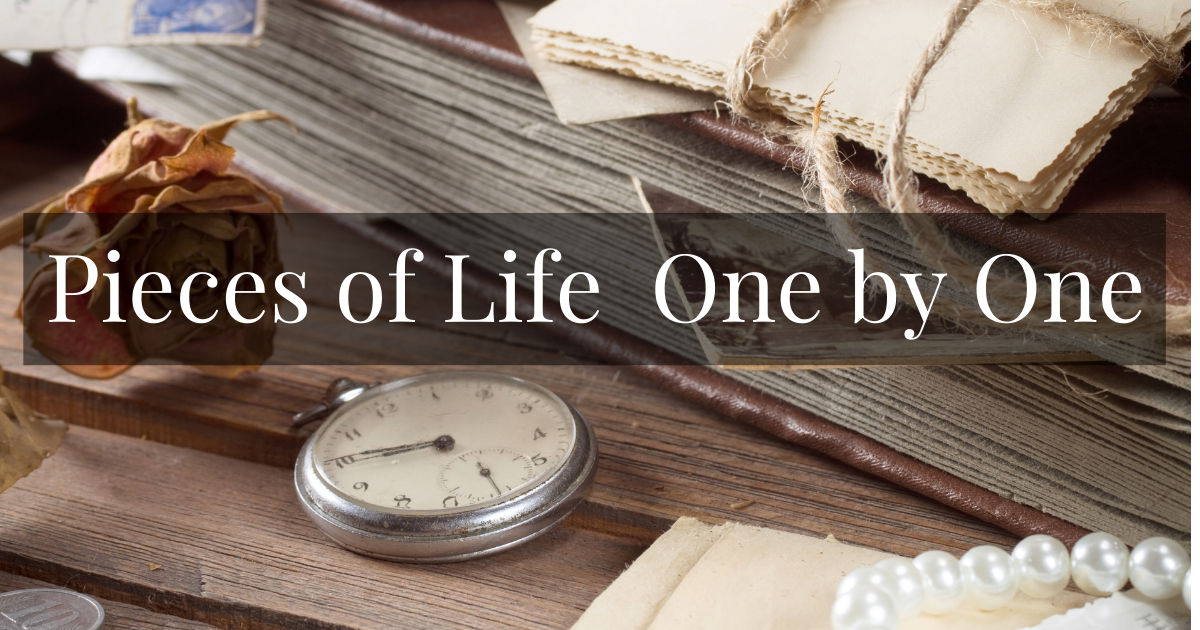
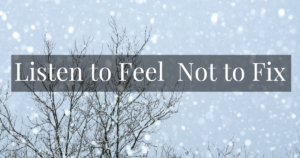



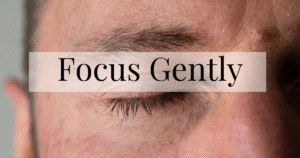

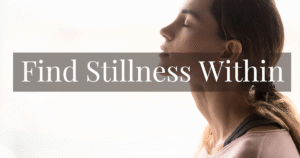
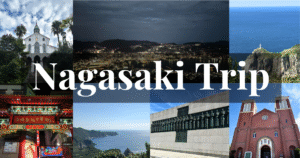
コメント