認知症の方と日々向き合う中で、「どう関わればいいのか」と悩む瞬間はありませんか?
私自身、義母や職場での認知症の方との関わりを通してその難しさと深さに何度も直面しました。
短期記憶は失われても、思いやりや気遣いといった「人としての土台」はしっかりと残っている――
そんな姿に触れるたび、認知症とは「記憶の病気」であっても、「心がなくなる病気」ではないことを改めて感じます。
認知症と“人格”は別のもの
「同じことを何度も言ってしまう」
「話の辻褄が合わない」
そんな変化に私たちはつい目を向けがちですが、
その人がかつてどう生きてきたか、どれだけ人に気を遣い、誠実に生きてきたか――
それは今も、言葉の端々や仕草の中に息づいています。
私の義母も、記憶が曖昧になってからも、
「ありがとうね」「いつも悪いね」
そんな言葉を何度もかけてくれました。
どんなに混乱しても、人としてのやさしさは、決して消えないのだと思います。
出口のない渦の中で
でも同時に、認知症の方は「自分の状態に違和感を持ち続けている」ようにも見えます。
「なんだか変だ」
「どうして思い出せないのか」
「さっきまでここにいた人が、もういないの?」
そんな“納得できない世界”に一人取り残されたような不安の中で、
必死に自分を律し、何とか現実に適応しようとする――
その姿に、こちらの胸が締めつけられるような思いになります。
そしてその混乱が進めば、「盗られた」「だまされた」といった被害妄想につながることもあります。
いくら「違うよ」と否定しても、本人には現実の感覚としてそれが“本当”に感じられる。
ここで私たちがどう対応すればよいのか、その正解は簡単には見つかりません。
相手を思いやることと、自分を守ること
家族や介護者として、その人の尊厳を守りたい。
けれど、自分自身の心や生活が壊れてしまっては意味がない。
「優しくしたいのに、もう限界」
そんなジレンマに、多くの方が悩んでいます。
だからこそ、「寄り添い方に正解はない」と知ること、
そして、「揺れる気持ちを抱えたままでもいい」と自分を許すことが大切だと感じます。
自分が“その立場”になったら
私は時々、自分が将来認知症になったら、どうしてほしいのだろうと考えます。
おそらく――
● 怒らずに、穏やかにいてほしい
● 間違っても、バカにしないでほしい
● 自分の言葉を、無視しないでほしい
● たとえ話が通じなくても、「今」の自分を受け止めてほしい
そして同時に、やはり**「できるだけ周りに迷惑をかけたくない」**という気持ちもあると思います。
自分のせいで誰かが苦しむのは望まないし、たとえ認知症になっても、そうした「人としての配慮」はきっと消えないのではないでしょうか。
そんなふうに考えると、目の前にいる認知症の方の中にも、同じような想いがあるのかもしれません。
その「人」としての声にならない願いを、できる限り大切にしたいと、私は思います。
まとめ:問いを抱えたままで、いい
「何が正解かわからない」
「もっと良い関わり方があるのではないか」
「この人にとって本当に幸せな時間ってなんだろう」
そんな“モヤモヤ”を抱えることは、
実は介護にとって、とても自然で、
そして大切なことかもしれません。
問いを持ち続けること――
それこそが、その人の「人としての尊厳」に向き合っている証だと、私は信じています。
あわせて読みたい記事


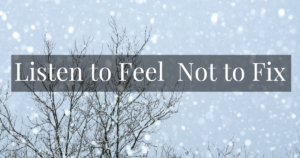



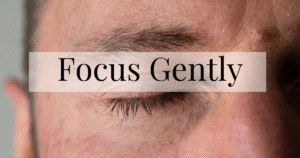

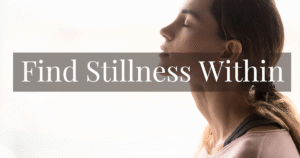
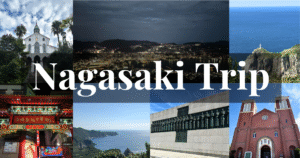
コメント