「やっと退院できたね」
そう声をかけながらも、娘の歩く様子を見て私は少し驚きました。あんなに元気だったのに、わずか半月の入院生活で足取りはふらつき、表情もどこか疲れたまま。病気そのものが回復に向かっていた一方で、“別のダメージ”が確かに残っていたのです。
今回は、娘の退院をきっかけに気づいた「入院生活が体と心に及ぼす影響」についてお話しします。
入院は「治療」だけじゃない──体力・筋力の低下
入院というと、病気の治療を受け、回復するための場所だと多くの人が思うでしょう。もちろんそれは間違いではありません。しかし実際には、**安静が続くことによる“身体機能の低下”**が、特に高齢者にとっては大きなリスクになるのです。
若い娘でも感じた体の衰えと心の葛藤
私の娘はまだ若い世代。それでも、入院中はベッドで過ごす時間が多く、歩く機会もほとんどありませんでした。
退院から数日後、「自然を感じたい」と娘の希望で、彼が車で海まで連れて行ってくれました。潮風にあたり、海を眺めながら穏やかな時間を過ごしたのはほんのひととき。その後、娘は強い疲労感を訴え、足元はふらつき、顔色も悪くなってしまったのです。
帰宅後、ベッドに横になったまま、娘はつぶやきました。
「できるつもりのことが、できない…」
その言葉には、自分の体が思い通りにならないことへの驚きと戸惑い、そして静かなショックがにじんでいました。
頭では「もう退院したんだから大丈夫」と思っていた。けれど、実際の体はまだ以前とはまるで違う。「できるはず」という気持ちと、「できない現実」の間にあるギャップが、娘の中に焦りや悔しさを生んでいたのだと思います。
高齢者の場合のリスクはもっと大きい
特に高齢者が入院した場合、その影響はさらに深刻です。医療の現場では「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」と呼ばれ、数日〜数週間の安静でも筋力・心肺機能の著しい低下、認知機能の低下、食欲不振、便秘などを引き起こすことがあります。
そして一度失った体力は、年齢を重ねるほどに回復までに時間がかかりやすくなります。場合によっては、元の生活には戻れず、要介護状態へ移行するケースもあるほどです。
薬の副作用がもたらす“別の苦しみ”
もう一つ、娘の退院後に私たちが直面したのが薬剤の副作用です。
肝臓への負担と吐き気
感染予防のために使われた抗生物質、そして痛み止め。これらの薬を継続的に使用していた娘は、ある時から強い吐き気を訴えるようになりました。検査の結果、肝臓の数値に変化があり、薬剤性の影響が疑われました。
「薬で治っていくのに、同時に別のところが弱っていくなんて…」
そう嘆いた娘の姿を見ながら、病気を治す過程そのものが体の他の部分に新たな負荷をかけるという現実を、私は身をもって知ることになりました。
一つの病気が、人生全体に影響するということ
病気というのは、単体で終わるものではありません。娘の場合は「腰椎の欠損」という明確な診断がありましたが、それだけを治せば元通り、というものではありませんでした。
・歩く力の低下
・肝機能の負担と体調不良
・日常生活への自信の喪失
これらすべてが、一つの病気が連鎖的に与える影響です。これは、高齢の家族を介護している方なら、きっと感じたことがあるのではないでしょうか。
「元気だったあの人が、入院を境に急に衰えたように見える」
そんなとき、目に見えない変化が確実に起きているのです。
健康な日常は、奇跡のようなバランスの上にある
退院後、娘は少しずつ筋トレやストレッチを始め、食事も気をつけるようになりました。最初は少し歩くだけでも疲れていたのに、今では買い物に出かける元気も戻ってきています。
健康とは、「病気じゃないこと」ではなく、体のすべての働きがバランスよく保たれている状態なのだと、今回の出来事を通じて改めて感じました。
体力、内臓、心、生活環境──どれか一つが崩れると、あっという間に全体のバランスが傾いてしまう。だからこそ、今ここに「普通に過ごせる日々」があることに、感謝の気持ちを持てるようになったのです。
今日からできる一歩:回復の時間を焦らない
もしご自身やご家族が入院したとき、退院後の回復のプロセスにも目を向けてみてください。焦らず、少しずつ歩みながら、「元気」を取り戻すこともまた、治療の一部です。
あなた自身も、どうかご自身の体と心に優しく、ゆっくりと向き合ってください。
「今日、こうして食事をして、会話して、歩けること」──それはとても特別なことなのだと、私たちは娘から教わった気がします。
合わせて読みたい記事


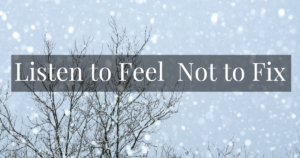



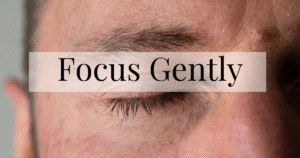

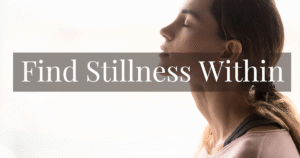
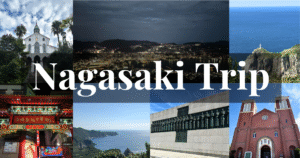
コメント