介護という現実の中で、お酒が心の支えになっている人は少なくありません。特に、男性が一人で認知症の親を介護しているような状況では、仕事と介護の板挟みのストレスから「夜の一杯」が欠かせないものになっていることもあるでしょう。
「お酒ぐらい、いいじゃないか」と思う気持ちも自然なもの。しかし、飲酒と健康の関係について知ったうえで、上手に付き合っていくことが、あなた自身の健康を守ることにもつながります。この記事では、介護ストレスと飲酒、適量の飲酒習慣、アルコールと健康リスクについてわかりやすく解説します。
飲酒がもたらす健康への影響とは
適度な飲酒にはリラックス効果や社交性の促進など、プラスの側面もあります。しかし、過度な飲酒が続くと、さまざまな健康リスクが生じます。
● 肝臓への負担
アルコールは肝臓で分解されますが、過剰摂取が続くと脂肪肝やアルコール性肝炎、最悪の場合は肝硬変に至ることもあります。
● 高血圧・心疾患のリスク増加
飲酒は一時的に血管を広げますが、継続的な多量飲酒は血圧を上昇させ、心臓への負担を大きくします。
● 睡眠の質の低下
「飲むと眠れる」と感じるかもしれませんが、アルコールは深い眠りを妨げ、夜中に目が覚めやすくなるため、結果として疲れが取れにくくなります。
● メンタルへの影響
一時的なストレス解消になっても、アルコールは神経伝達物質に作用し、長期的にはうつ症状を悪化させる場合もあります。
「お酒くらい、いいじゃないか」と思うあなたへ
あなたは、親を自宅で介護しながら、日中は仕事をしているかもしれません。誰にも頼れない日もあるし、相談できる相手もいない。だからこそ、「お酒の時間くらい自由でいたい」と思うのも無理はありません。
しかし、毎日のように飲むお酒が、あなたの疲れを取るどころか、体にじわじわと負担をかけていたとしたら──。
介護中の飲酒習慣を見直すことは、将来の自分を守ることにもつながります。介護は長期戦です。自分の健康をないがしろにすると、介護を続けられなくなる恐れもあるのです。
健康を守る「ほどよい飲み方」とは?
無理に禁酒する必要はありません。でも、ほんの少しだけ「距離感」を見直してみることはできます。
● 週に2日は“休肝日”を作る
肝臓を休ませる時間を意識的に取ることで、負担を軽減できます。
● 飲む量を測ってみる
ビールなら350ml缶1~2本、日本酒なら1合が“適量”とされています。それを超える量が習慣化していないか、確認してみましょう。
● ノンアル飲料を活用
最近のノンアルコール飲料は味も豊かで満足感も高く、代替として十分活躍します。
● 飲む目的を「楽しむ」に戻す
ストレス発散の手段ではなく、「おいしいから」「雰囲気を楽しむために」という本来の目的に立ち返ってみましょう。
健康的な習慣をひとつだけ取り入れてみる
お酒との関係を見直すことは、「自分の身体とちゃんと向き合う」ことでもあります。忙しい介護生活の中でも、少しの工夫で健康的な習慣は取り入れられます。
- 夜のストレッチや深呼吸でリラックスする
- 食事のバランスを見直す(野菜やタンパク質をしっかり)
- 軽い運動を日課にする(散歩やラジオ体操やヨガなど)
こうした行動は、飲酒による健康リスクの予防にもつながります。
おわりに:あなたの健康が、介護を続ける力になる
お酒はあなたを癒してくれる存在であると同時に、使い方を間違えるとあなたを追い詰める存在にもなり得ます。
自分の体調や気持ちと向き合いながら、「飲むこと」と「健康を守ること」のバランスを考える。それは、単なる“健康管理”ではなく、あなたがあなたらしく生きるための選択です。
介護と健康管理の両立を意識しながら、これからも大切な日々を、心と体の両方から支えていけますように。


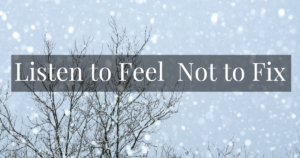



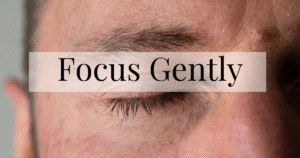

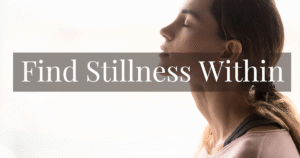
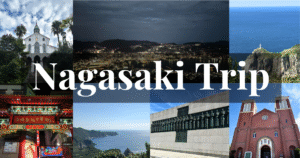
コメント